「白湯」は、一度沸騰させた水を50℃前後まで冷ましたもので、体を温めることを目的とした飲み物です。代謝のサポートや冷え対策に適しており、健康維持の一環として取り入れられています。
一方、「湯冷まし」は、沸騰後に30℃以下、または常温まで冷ました水で、赤ちゃんのミルク作りや体調不良時の水分補給に適しています。
どちらも加熱後に冷ました水という点では共通していますが、それぞれの特性を理解し、適切なシーンで飲むことが大切です。
ここでは、白湯と湯冷ましの違いや、それぞれの正しい飲み方、メリットについて詳しく紹介します。
- <ご注意>
- 本記事の内容は、白湯の健康効果やダイエット効果などを保証するものではありません。
特に、健康維持や改善を目的として白湯を取り入れる際は、かかりつけ医や専門機関に相談のうえ、ご自身の体調に合った方法で実践してください。
白湯と湯冷ましの違いとは?
「白湯」と「湯冷まし」は、どちらも水を加熱した飲み物ですが、その作り方や特徴には違いがあります。
白湯は、水を一度沸騰させてから飲める温度まで冷ましたもので、体を内側から温める効果が期待されています。
一方、湯冷ましは、沸騰させた水を常温まで冷ましたもので、赤ちゃんのミルク作りや水分補給に適しています。これらの違いを理解し、目的に応じて使い分けることが大切です。
白湯の温度
白湯とは、水を沸騰させた後に50℃前後まで冷ましたものをいいます。
湯冷ましの温度
湯冷ましは30℃以下、場合によっては常温(20℃前後)まで冷まされます。
白湯とは?
先程も紹介した通り、白湯は、水を一度沸騰させた後に50℃前後まで冷ました飲み物のことをいいます。
古くから体を温める健康法として親しまれ、冷え性の改善、消化のサポート、デトックス効果などが期待されています。特に朝起きたときに飲むと、胃腸を温めて働きを活発にし、代謝を促すといわれています。
白湯はシンプルな飲み物ですが、その作り方や飲み方によって効果が変わるため、正しい方法を知ることが重要です。
白湯の正しい作り方
白湯を作る際には、水をしっかりと沸騰させることがポイントです。
一般的にはやかんや鍋を使って水を沸騰させ10分ほど沸かし続けます。これによって水の中の塩素やトリハロメタンなどの不純物を飛ばし、まろやかで飲みやすい白湯を作ることができます。
沸騰させる際は、やかんのふたを開けて蒸気を逃すと、不純物が蒸気となって取り除かれます。
美味しい白湯を作るコツ
美味しい白湯を作るためには、水の選び方も重要です。水道水を使う場合は、しっかりと沸騰させてカルキを飛ばしますが、軟水のミネラルウォーターを使用すると、より飲みやすくなります。
また、飲む温度は50℃前後が理想とされ、熱すぎると内臓に負担がかかり、冷たすぎると体を温める効果が得られにくくなります。
ちなみに、多くのミネラルウォーターは、塩素やトリハロメタンが含まれていないことから、わざわざ沸騰させることはありません。
白湯の正しい飲み方とタイミング
白湯は、飲むタイミングによって得られる効果が異なります。
朝起きた直後に飲むと胃腸を温め、代謝を活発にするといわれています。
また、夜寝る前に飲むとリラックス効果が高まり、睡眠の質が向上するといわれています。一度にたくさん飲むのではなく、ゆっくりと少しずつ飲むことが大切です。
ちなみに、食後はすぐに飲むと消化スピードが落ちるといわているので、しばらくたってから飲むようにしましょう。
白湯を飲むメリット・デメリット
白湯は、体を内側から温めるだけでなく、消化をサポートし、老廃物の排出を促すなど、健康維持に役立つといわれています。
しかし、適量を守らずに飲みすぎると体調を崩す可能性もあります。白湯のメリットを最大限に活かすためには、正しい飲み方や適量を理解することが大切です。
白湯を飲むことで得られるメリット(健康効果)
白湯を飲むことで、以下のような健康効果が得られるといわれています。
- (1) 冷え性の改善
- 温かい飲み物をとることで体の内側から温まり、血行が促進されます。特に冬場や冷え性の方にはおすすめです。
- (2) 消化のサポート
- 白湯が胃腸を温めることで消化機能が活発になり、胃もたれや便秘改善につながるといわれています。
- (3) デトックス効果
- 白湯を飲むことで内臓の働きが活発になるため、老廃物の排出が促されます。朝一番に飲むと、睡眠中に溜まった毒素の排出を助けるといわれています。
- (4) リラックス効果
- 白湯をゆっくりと飲むことで副交感神経が優位になり、ストレスの緩和や睡眠の質向上につながるといわれています。

白湯を飲みすぎた場合のデメリット
白湯は健康に良いとされていますが、過剰な摂取はおすすめできません。
以下のような点に注意しましょう。
- (1) 水中毒のリスク
- 短時間に大量の白湯を飲むと、体内のナトリウム濃度が下がり、水中毒の原因になる可能性があります。特に1時間以内に1リットル以上飲むのは避けたほうが良いとされています。
- (2) 胃酸の薄まりによる消化不良
- 食事が終わった直後に大量の白湯を飲むと胃酸が薄まり、消化不良を引き起こすといわれていいます。食後は30分以上時間をあけてから飲みましょう。
- (3) 過剰な発汗や頻尿
- 白湯を飲みすぎると、発汗や排尿が増え、逆に体の水分バランスを崩す可能性があります。特に夜間の過剰摂取は睡眠を妨げることもあるため注意しましょう。
湯冷ましとは?
先程も紹介しましたが、「湯冷まし」とは、水を一度沸騰させた後、常温または適温まで冷ました飲み物のことをいいます。
白湯とは異なり、体を温める目的ではなく、飲みやすくするためや衛生面を考慮して作られます。特に赤ちゃんのミルク作りや水分補給、体調が優れないときの水分摂取に適していることから、昔から健康管理の一環として活用されてきました。
湯冷ましがよく選ばれる場面
湯冷ましは、以下のようなシーンで利用されることが多いです。
- (1) 赤ちゃんのミルク作り
- 粉ミルクを適温の湯冷ましで溶かすと飲みやすくなります。
- (2) 赤ちゃんの水分補給
- 母乳やミルクの合間に適量の湯冷ましを与えることで、赤ちゃんの水分補給をサポートすることができます。
- (3) 体調が悪いときの水分補給
- 風邪や胃腸の調子が悪いとき、冷たい水よりも湯冷ましの方が体に優しく、消化器官に負担をかけません。
- (4) 便秘解消のサポート
- 湯冷ましを飲むことで腸の動きを促し、便秘の改善に役立つことがあります。
便秘に困っているときに湯冷ましが役立つ理由
湯冷ましは、腸内環境を整えるのに役立つ飲み物の一つといわれています。
特に、朝起きたときに飲むと腸の運動が活発になります。冷たい水を飲むと胃腸が冷えてしまい、逆に腸の動きが鈍くなることがありますが、湯冷ましであれば程よく体に負担をかけずに水分を補給できるため、便秘改善の一助になるといわれています。
赤ちゃんのミルクや水分補給に湯冷ましが適している理由
赤ちゃんにとって、安全な水分補給は非常に重要です。湯冷ましを使用することで、以下のようなメリットがあります。
- (1) 不純物のリスクを抑える
- 水道水や市販のミネラルウォーターには不純物(ミネラル分を含む)が含まれていることがありますが、湯冷ましはそれらのリスクを軽減できます。
- (2) 赤ちゃんの未熟な腎臓に優しい
- 赤ちゃんの腎臓はまだ発達途中のため、ミネラルを多く含む水は負担になることがあります。湯冷ましはミネラルが少なく、赤ちゃんの体に優しい飲み物です。
- (3) 適温で飲みやすい
- 赤ちゃんは熱い飲み物をそのまま飲むことができないため、適温に冷ました湯冷ましは飲みやすく、水分補給に適しています。
このように、湯冷ましは赤ちゃんや体調が優れない人にとって、安全かつ負担の少ない飲み物として重宝されています。
湯冷ましの作り方
湯冷ましは、一度水を沸騰させてから適温まで冷まして作ります。
加熱することで水道水に含まれる塩素や不純物を取り除くことができ、より安全に飲むことができます。
作り方には、やかんや鍋、電子レンジ、電気ケトルなどの方法があり、それぞれの手順を理解することで、用途に合わせた湯冷ましを簡単に作ることができます。
やかん・鍋で作る方法
- 水をやかんまたは鍋に入れ、火にかける。
- 10分ほど火にかけてしっかり沸騰させる(塩素などの不純物を飛ばすため、ふたは開けておく)
- 常温または適温まで冷ます。
電子レンジで作る方法
- 耐熱容器に水を入れる。
- 500W?600Wの電子レンジで約2?3分加熱し、しっかり沸騰させる。
- その後、適温まで冷ます。
電気ケトルで作る方法
- 電気ケトルに水を入れ、スイッチを入れて沸騰させる。
- 沸騰後、ふたを開けたまましばらく冷ましておく。
冬だけじゃない!夏にも役立つ白湯・湯冷ましの活用法
白湯や湯冷ましは寒い季節に体を温める飲み物として知られていますが、実は夏にもさまざまなメリットがあります。
暑い時期に冷たい飲み物をとりすぎると、内臓が冷えて消化機能が低下したり、血流が悪くなったりすることがあります。
そこで、適温の白湯や湯冷ましを上手に取り入れることで、夏バテの予防や水分補給に役立てます。
また、エアコンの効いた室内では体が冷えやすくなっています。そんなときに白湯を飲むと体の内側からじんわりと温まります。
湯冷ましは冷たい水よりも胃腸に優しくこまめな水分補給にも適しています。暑い季節でも健康的に過ごすために、白湯や湯冷ましを上手に活用しましょう。
忙しい朝でも簡単に白湯・湯冷ましを取り入れるコツ
朝は何かと忙しく、白湯や湯冷ましを作る時間がない方も多いと思います。しかし、ちょっとした工夫をすることで、手間をかけずに朝の習慣として取り入れることができます。
白湯や湯冷ましを飲むことで、胃腸が目覚め、体が温まり、スッキリとした一日をスタートできるので、ぜひ朝のルーティンに加えてみましょう。
- (1) 前日の夜に準備しておく
- 忙しい朝に白湯を作るのが面倒な場合は、前日の夜にお湯を沸かし、保温ポットや魔法瓶に入れておくのがおすすめです。朝になったらそのままカップに注いで飲むだけなので、時間のない朝でもすぐに飲むことができます。
- (2)電気ケトルや電子レンジを活用する
- やかんや鍋でじっくりと沸かすのが理想的ですが、時間がないときは電気ケトルを使えば短時間で沸騰させることができます。また、電子レンジもおすすめです。
- (3)適温に冷ます時間を短縮する
- 白湯や湯冷ましは、適温まで冷ますのに時間がかかることがあります。朝の時間を有効に使うためには、「水を入れて冷ます」「氷を入れて冷ます」などの方法がおすすめです。
白湯を飲むときにウォーターサーバーがあると便利な理由
白湯を毎日の習慣にするなら、ウォーターサーバーを活用することで、より手軽に続けられます。以下の理由から、家庭で白湯を飲む際にはウォーターサーバーの利用がおすすめです。

- (1)いつでも適温の白湯がすぐに作れる
- ウォーターサーバーがあれば、ボタンひとつで温水を利用でき、冷水と混ぜることで、すぐに適温の白湯を作ることができます。やかんや鍋で沸騰させて冷ます手間が省けるため、忙しい朝や就寝前などにも手軽に飲むことができます。
- (2)水質が安定しており安心
- ウォーターサーバーの水は、多くが浄水処理されています。煮沸による塩素の除去などを気にすることなく、安心して白湯を楽しめます。
- (3)家族全員が手軽に白湯を取り入れやすい
- キッチンでお湯を沸かす手間が不要になり、家族全員が好きなタイミングで簡単に白湯を作れるようになります。火を使うことがないため、子どもや高齢者も安全に白湯を作ることができます。
- (4)生活スタイルに合わせて活用できる
- ウォーターサーバーは白湯を飲むだけでなく、お茶やスープ作り、料理にも活用できるため、日常のさまざまなシーンで役立ちます。
- (5)継続しやすく、白湯の習慣を無理なく続けられる
- 白湯の習慣は続けることが大切ですが、手間がかかるとなかなか続きません。ウォーターサーバーがあれば、手軽に白湯を作れるため、無理なく毎日の生活に取り入れることができます。
ボトル型ウォーターサーバーをおすすめする理由
ボトル型ウォーターサーバーは、水の味や品質を重視しています。また、災害時の備蓄水として利用したい人にもおすすめです。
天然水や高度浄水の水が楽しめる
ボトル型ウォーターサーバーは、天然水や高度に浄化された水が飲めるため、水の味を重視したい人に最適です。
災害時や非常時の備蓄水になる
ボトル型ウォーターサーバーは、大容量の水をボトルでストックできるため、災害時や断水時の備蓄水としても活用できます。
初期工事が不要で設置が簡単
ボトル型ウォーターサーバーは、水道工事や複雑な設置手順が必要ありません。届いたその日から簡単に始められます。
使い終わったボトルは回収される
使用後の空ボトルは業者が回収する仕組みになっている場合が多く、ゴミとして処理する手間が省けます。リサイクルにも対応しているため、環境への負荷も軽減されます。
水の消費量に合わせてボトルを選べる
提供する会社によりますが、家庭やオフィスの水の使用量に応じて、ボトルのサイズや配送頻度を選択することができます。使用頻度に応じた柔軟なサービスが魅力です。
温水・冷水がいつでも利用可能
多くのボトル型ウォーターサーバーは冷水と温水機能を備えています。お湯は白湯やお茶だけではなく、カップラーメンなどを食べる際にも便利です。
アルピナウォーターのご利用はいかがですか
ボトル型ウォーターサーバー「アルピナウォーター」は、北アルプスの名水を原水とし、NASA開発の「ROろ過システム」で分子レベルまで磨き上げた純度99.9%のピュアウォーターです。
硬度1.05の超軟水で飲みやすく、赤ちゃんのミルク作りや調理にも最適です。
さらに、国際認証「ISO22000」「FSSC22000」を取得した無菌工場で生産されており、安全性にも配慮しています。
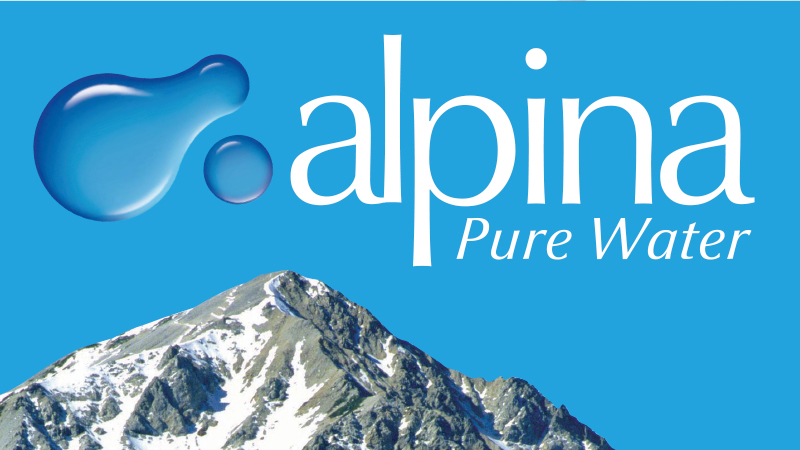
<アルピナウォーター(ボトル型)をおすすめする理由>
- (1)リーズナブルな価格「500mlあたり、51.75円!」
- アルピナウォーターは、12Lボトルが1本1,242円(税込)で、500mlあたり51.75円と非常にお得な価格設定です。高品質なピュアウォーターを、手頃なコストで楽しめます。
- (2)欲しいときに欲しいだけ注文できる
- 定期購入の必要がなく、必要な時にオーダーできるため、使う量に応じて自由に調整が可能です。月の購入ノルマがないため、一人暮らしや旅行が多い方でも安心して利用できます。
- (3)無料宅配サービス
- 配送エリア内であれば、配送料が無料。追加注文時も、12Lボトル3本からのオーダーで、追加費用なしで届けてもらえます。
- (4)空きボトルの無料回収
- 使用後の空きボトルを無料で回収します。ゴミが出ず、家庭内での処理が不要です。
- (5)手軽にはじめられる
- 会員登録なしで利用を開始できるため、「まずは試してみたい」という方にも気軽にお試しいただけます。
温活(おんかつ)に白湯を取り入れる
温活(おんかつ)とは、体を冷やさずに温める習慣を取り入れることで、血行を促進し、基礎体温を上げることを目指す健康習慣のことです。
冷えは、血流の低下や代謝の低下につながり、疲れやすさや免疫力の低下などの原因になると考えられています。
白湯を飲むことは手軽な温活です。先ほどから紹介しているように、適切な量やタイミングを守り、しっかり体をやさしく温めましょう。
白湯をより楽しむ工夫
白湯はそのままでも飲みやすいのですが、ショウガやシナモン、はちみつを加えることで風味が豊かになり、より飲みやすくなります。
これにより、白湯を取り入れる習慣が楽しくなり、継続しやすくなるのも魅力です。アレンジした白湯を取り入れることで、温活を楽しみながら体を温めましょう。
無理なく続けることが大切
温活は、日々の生活の中で少しずつ取り入れることが重要です。白湯を飲むことを習慣にするだけでも、手軽に始められる温活のひとつです。自分に合った方法で、無理なく続けてみてはいかがでしょうか。
まとめ
白湯と湯冷ましはどちらもシンプルな飲み物ですが、その違いや適した飲み方を知ることで、より効果的に健康習慣として取り入れることができます。
白湯は体を温め、代謝を促進する働きがあり、特に冷え性の改善や消化を助ける効果が期待できます。一方で、湯冷ましは胃腸に負担をかけずに水分補給をしたいときや、赤ちゃんのミルク作りに最適な飲み物です。
「忙しくて白湯を作る時間がない」「続けられるか不安…」という方も、ウォーターサーバーなどを活用することで、簡単に日々の習慣として取り入れることができます。
健康は、毎日の小さな積み重ねから。毎日の生活に白湯や湯冷ましを上手に取り入れてみましょう。
Q&A(白湯と湯冷ましの違いについて)
- Q.白湯と湯冷ましの違いは何ですか?
- A.白湯は一度沸騰させた水を50℃前後まで冷ましたもので、体を温めることを目的としています。一方、湯冷ましは沸騰させた水を常温(30℃以下)まで冷ましたもので、赤ちゃんのミルク作りや水分補給に適しています。
- Q.白湯の適切な温度は何度ですか?
- A.白湯の適温は約50℃前後とされています。これ以上熱いと内臓に負担がかかり、冷たすぎると体を温める効果が得られにくくなります。
- Q.白湯を作る際のポイントは何ですか?
- A.水をしっかり沸騰させ、約10分間沸かし続けて不純物を飛ばすことです。やかんのふたを開けて蒸気(不純物)を逃がしましょう。
- Q.白湯を飲むタイミングはいつが良いですか?
- A.朝起きた直後に飲むと胃腸を温め、代謝を促すといわれています。夜寝る前に飲むとリラックス効果が高まり、質の良い睡眠につながることが期待されます。
- Q.白湯を飲みすぎるとどのようなデメリットがありますか?
- A.過剰摂取は水中毒のリスクを高める可能性があり、また胃酸が薄まることで消化不良を引き起こすことがあります。
- Q.湯冷ましはどのような場面で活用できますか?
- A.赤ちゃんのミルク作りや水分補給、胃腸が弱っているときなどに適しています。また、便秘改善のサポートになるといわれています。
- Q.湯冷ましを作る際の注意点は?
- A.一度しっかり沸騰させて塩素などの不純物を取り除くことが重要です。また、赤ちゃんに与える場合は硬水ではなく軟水が適しています。
- Q.白湯を飲むとどのような健康効果が期待できますか?
- A.白湯は冷え性の改善、消化のサポート、デトックス効果、リラックス効果などが期待されています。特に朝一番に飲むことで、胃腸の働きを活発にし、老廃物の排出を促すといわれています。
- Q.忙しい朝に白湯を手軽に飲む方法はありますか?
- A.前夜に白湯を作り、保温ポットに入れておくと、朝すぐに飲むことができます。また、ウォーターサーバーを活用すれば、簡単に適温の白湯を用意できます。
- Q.ウォーターサーバーを利用すると白湯作りが楽になる理由は?
- A.ボタンひとつで温水が出るため、すぐに白湯を用意できます。冷水と混ぜることで適温に調整しやすく、火を使わないため安全性も高いです。また、水質が安定しているため、安心して飲むことができます。
<参考文献>
神戸市外語大学「保険だより」
https://www.kobe-cufs.ac.jp/campuslife/files/2023autumn3.pdfジェイクト健康保険組合「白湯を活用して体調管理」
https://www.jtekt-kenpo.or.jp/health_promotion/communication/pdf/71/02.pdf


